「五十肩は自然に治る」と聞いたことがあるかもしれません。
確かにそういうケースもありますが、実際には時間がかかることが多く、対応を間違えると悪化することもあります。
今回は、五十肩がどのような流れで回復していくのか、3つの時期(フェーズ)に分けて解説します。
五十肩には“3つの時期”があります
五十肩(肩関節周囲炎)は、進行具合によって対応が大きく異なります。
それを知らずに無理をしてしまうと、痛みが長引いたり、関節が固まってしまうことも。
① 【急性期】炎症が強く、痛みが激しい時期(〜発症後約2週間〜2ヶ月)
- 動かしていなくてもズキズキ痛む(夜間痛が強い)
- 腕を上げる・回すなど、動きで鋭い痛みが出る
- 安静にしていても生活に支障が出ることがある
対応のポイント:
- 無理に動かさないことが最優先
- 湿布や冷却、可能なら医療機関の受診も検討
- この時期は“痛みを増やさない”ことが回復への第一歩
② 【拘縮期】痛みが落ち着き、動かしにくくなる時期(発症後2〜6ヶ月頃)
- 動かすと痛むが、安静時の痛みはやや軽くなる
- 肩が固まって「可動域が狭い」状態になる
- 髪を結ぶ・服を着るなどの日常動作に困る
対応のポイント:
- 無理のない範囲で少しずつ動かすことが大切
- 肩甲骨や体幹の動きも含めて“全体を整える”意識で
- 強い痛みがある日は無理せず、やさしい動きにとどめる
③ 【回復期】痛みは減り、動きが戻ってくる時期(半年〜1年以降)
- 動かせる範囲が少しずつ広がる
- 痛みが軽くなってきて日常生活も少しずつ楽になる
- 筋力や柔軟性が落ちているため、再調整が必要
対応のポイント:
- この時期にしっかり動かして可動域を回復させることが重要
- 肩だけでなく、姿勢や全身の使い方も見直すタイミング
- セルフケアや運動療法を“やりすぎず、継続する”ことがポイント
整体師として伝えたいこと
五十肩の回復は「ただ待つ」だけではスムーズにいかないケースが多くあります。
時期ごとの適切な対応を知り、無理せず、でも止めすぎずに体を整えていくことが、将来の後遺症を防ぐポイントです。
📩 ご相談・ご予約はこちらから
▶ LINEで予約する
次回は、回復期におすすめの肩の動かし方・セルフケアもご紹介していきます!
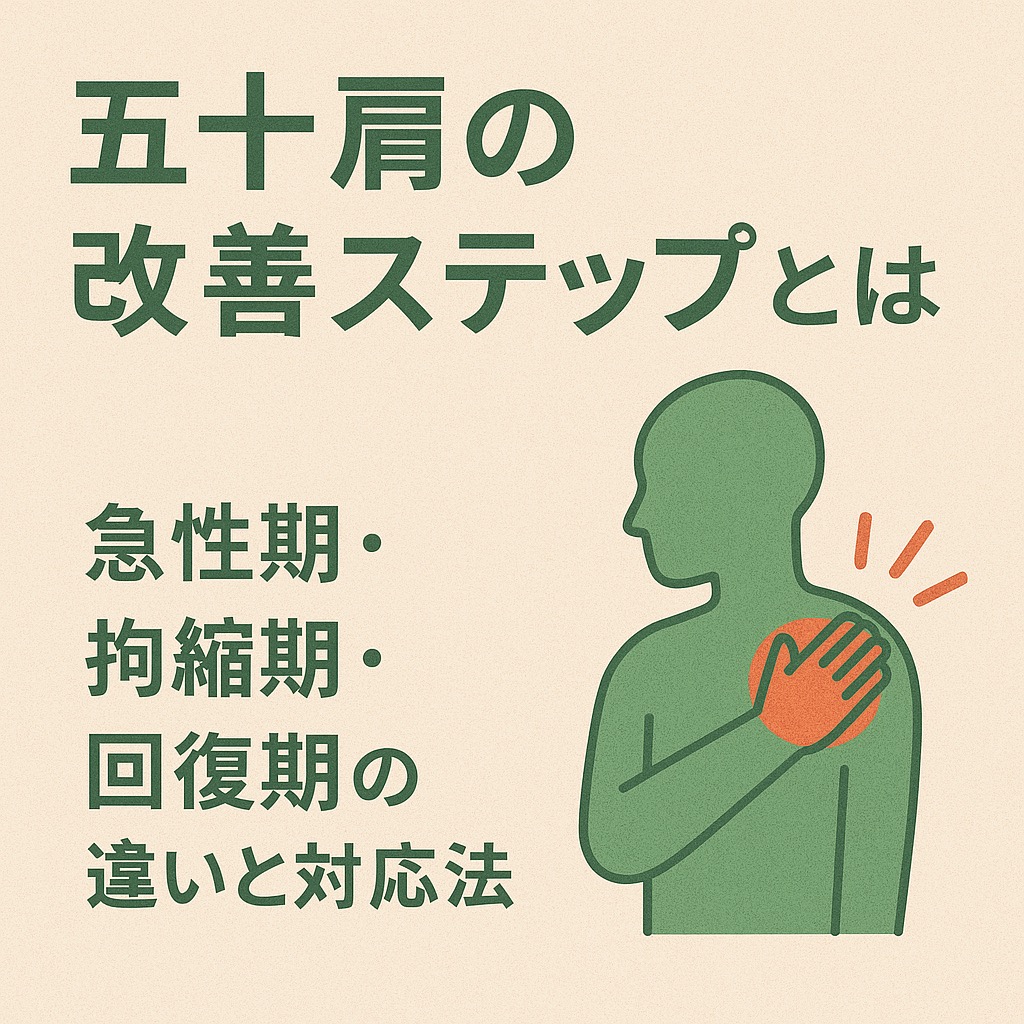

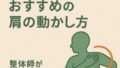
コメント